
再生医療を世界へ届けるために。羽田から始まる
ロート製薬&藤田医科大学のチャレンジ
馬渕 洋(藤田医科大学東京 先端医療研究センター 准教授)
野中 秀紀(ロート製薬 再生医療研究企画部)
公開日:2024年12月17日
内容、所属、役職等は公開時のものです
これまで有効な治療法のなかった疾患をも治療できるとして、大きな期待がかかる「再生医療」。ヒトが本来もつ“再⽣する⼒”を利⽤し、幹細胞などを用いて、病気・けがなどで機能を失った組織や臓器の機能を再生する治療です。日本では世界に先駆けて再生医療の法整備が進み、研究が進められています。
ロート製薬でも2013年から、幹細胞の一種である間葉系幹細胞などを用いた、再生医療の研究開発を組織として立ち上げ本格的にスタート。2023年には藤田医科大学と共同で、羽田に再生・細胞医療の研究講座を開設しました。藤田医科大学とロート製薬の知見を掛け合わせ、間葉系幹細胞の基礎研究を進めると同時に、実際にそれを患者さんに届けるべく臨床への応用も目指しています。
プロジェクトを主導するのは、間葉系幹細胞研究の第一人者として知られる藤田医科大学東京 先端医療研究センターの馬渕洋先生。そして、ロート製薬の再生医療事業に関わる野中秀紀です。間葉系幹細胞の可能性を信じ、研究に情熱を燃やす2人に、協業の背景や現在地、そして再生医療が社会に実装された先に訪れる未来についてうかがいました。

馬渕 洋藤田医科大学東京 先端医療研究センター 准教授
1979年、岐阜県生まれ。慶應義塾大学医学研究科博士課程修了、医学博士。生物の組織再生に興味を持ち、その再生のメカニズムに深く関わる「組織幹細胞」の研究を推進。特に、骨髄や脂肪に存在する間葉系幹細胞の細胞特性や生体内での役割解明に向け研究に励む。2022年国際幹細胞学会 (ISSCR) Next generation of leaders、2023年日本再生医療学会理事。2023年4月より現職。

野中 秀紀ロート製薬 再生医療研究企画部
1977年生まれ。埼玉県出身。2005年、東京大学大学院理学系研究科博士課程修了後、東京大学、マックスプランク細胞生物学・遺伝学研究所での博士研究員を経て、2014年にロート製薬株式会社に入社。入社後は再生医療研究企画部にて脂肪由来間葉系幹細胞を用いた再生医療等製品の開発・マネジメントに従事。
無限の可能性を秘める、間葉系幹細胞を用いた再生医療

——まずはじめに、野中さん、馬渕さんが「再生医療」や「間葉系幹細胞(※1)」の研究に携わることになったきっかけを教えてください。
野中 私は大学院を出た後、9年間アカデミアで研究員をしていました。研究分野は「発生生物学」や「細胞生物学」で、肝臓発生や再生をテーマに研究してきました。そのような中で、2013年にロート製薬が再生医療のプロジェクトを立ち上げて、研究員を探しているということで、私も縁あって2014年からチームに参加することになったんです。それから10年間、再生医療事業の研究開発に携わっています。
馬渕 私は、父が獣医師で研究をやっていたため、その影響が大きかったですね。「研究の道で生きていこう」とスイッチが入ったのは、人工皮膚の研究です。人工皮膚には「治癒を促進する」という能力があり、床ずれや火傷の治療に応用されています。この治癒を促進する細胞の一つが「間葉系幹細胞」だったことから、間葉系幹細胞を軸とした再生医療の研究につながっていったというのが、大まかな経緯です。
——再生医療に用いられる細胞は他にも「iPS細胞」や「ES細胞」などがありますが、馬渕先生が間葉系幹細胞の研究を長く続けている理由はありますか?
馬渕 間葉系幹細胞ってなかなか捉えどころのない細胞で、そこがおもしろいところでもあります。骨や脂肪からも採取することができて、個々の細胞で個性が違うにも関わらずそのすべてを同じように「間葉系幹細胞」と呼んでいるんです。研究領域も多岐にわたるため、いまだ解明されていない部分も多い。だからこそ、長い時間をかけて研究する価値があるんじゃないかなと。僕は骨も脂肪も、間葉系幹細胞にまつわることは全て興味の対象ですので、僕にしか見えない細胞の姿、価値の届け方があるのではないかと思い研究を続けています。
——自分を治癒させる細胞が自分の組織からとれるというのは、驚きですね。
馬渕 人は本来、治癒能力を持っていて小さな損傷であれば自然に治ります。その能力を活用して医療に利用できるのが再生医療の醍醐味です。自身の組織で、多くの人が治療できたらすごくいいですよね。脂肪だけでなく、臍帯(へその緒)や出産時に母体から娩出された胎盤からも間葉系幹細胞をとることができます。ですので、再生医療はある意味「エコ」なのかもしれませんね。
(※1)間葉系幹細胞……骨髄、脂肪、臍帯などから分離する幹細胞の一種。筋肉や軟骨、神経など、さまざまな種類の細胞に分化し得る特徴を持ち、再生医療への応用が進められている。
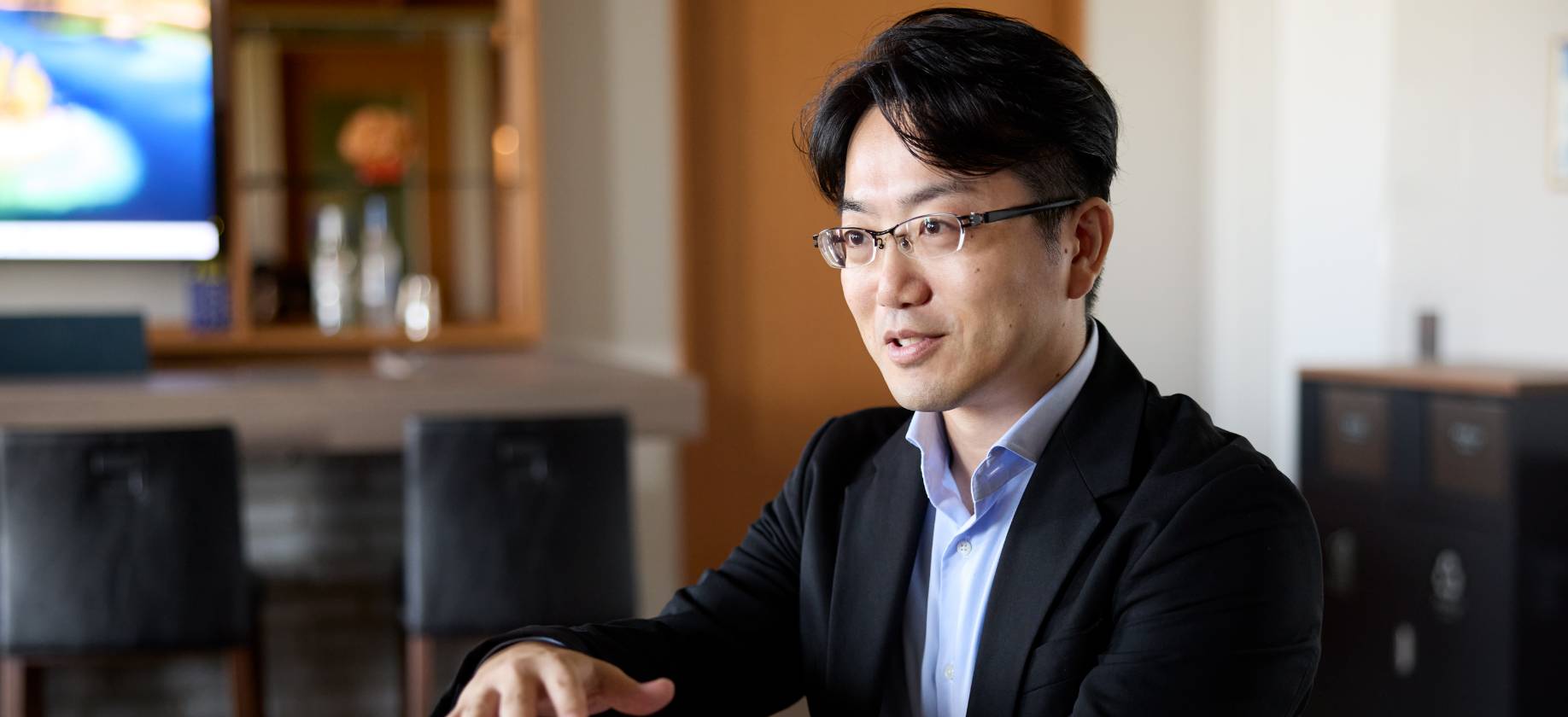
お互いの強みを生かして産学連携で「再生医療」の社会実装を目指す

——ロート製薬は2023年10月に藤田医科大学が開所した次世代医療・研究拠点の新施設「藤田医科大学東京 先端医療研究センター」に参画しました。参画の背景を教えてください。
野中 ロート製薬では、まさに先ほどの間葉系幹細胞をはじめとした細胞を用いた「再生医療」の領域に本格的に取り組み始め既に10年以上が経ちます。2016年以降、京都の研究開発拠点を始め、国内に複数の特定細胞加工物(※2)の製造許可を取得し、細胞製剤をいち早く患者さんへお届けできる体制づくりを推進しています。また、今後も再生医療を軸としたアンメットメディカルニーズ(※3)に対する研究をさらに推進しているなかで、藤田医科大学が羽田に新たなクリニックと研究拠点を設けることを知りました。藤田医科大学はここで、再生医療をはじめとする先端医療を研究し、どんどん患者さんに提供しようとしている。再生医療の社会実装、という同じ想いを持つロート製薬としては、ぜひここで一緒に取り組んでいきたい、と今回の参画にいたりました。
(※2)特定細胞加工物……再生医療を行うために製造される細胞薬などの加工物。「再生医療等安全性確保法」が定める厳格な基準に基づいて製造される必要がある。
(※3)アンメットメディカルニーズ……これまでの医療では有効な治療法が見つかっていない疾患に対する医療需要
——具体的に、ここでどんな共同研究や取り組みを行っていくのでしょうか?
野中 最も大きな柱は、再生・細胞医療を研究する共同研究講座の開設です。藤田医科大学とロート製薬の知見を用いて「間葉系幹細胞」の基礎研究を進めると同時に、実際に新しい治療を患者さんに届けるために、藤田医科大学 羽田クリニックの医師の方々と連携しながら臨床応用を目指した研究も進めていきます。将来、再生医療が治療の選択肢として身近になることを目指します。
馬渕 「再生医療」の基礎となる概念は古くから存在していて、2012年に、京都大学の山中伸弥先生たちがノーベル医学・生理学賞を受賞したことで一般にも広く知られるようになりました。しかし、再生医療を「誰もが」「普通に」受けられるようにはなってはいないのが現状です。
——確かに、10年以上前に「iPS細胞」や「再生医療」が一気に脚光を浴びましたが、その後どうなったのかはあまり知られていません。
馬渕 この技術を患者さんに届けるにあたって、大学の研究者の力だけでは限界があります。基礎研究結果が出たとしても、それを実際にヒトに用いた際の効果や安全性を検証する部分がどうしても弱いんです。また、研究の成果を世間に発信するという点でも課題がある。そうした弱点を補完するためには、企業を含めたさまざまな人とのネットワークを活用していかなければ難しいだろうと。だからこそ、今回の「再生・細胞医療開発講座」には大きな意義があります。
——馬渕先生としては、ロートと協業することでどんなシナジーを期待していますか?
馬渕 ロートさんは、やはり「医療を一般向けに広げる」という部分に大きな強みがあります。たとえば、従来は病院で診察を受けないと処方されなかったような医薬品や検査キットをOTC領域でドラッグストアなどを中心に展開し、身近なものにしてきた実績があります。再生医療についても同じで、一部の人しか受けられないのではなく、全国民が当たり前に受けられるくらい身近なものにしていくために、ロートさんの技術力や発信力は大きいと考えています。
野中 私たちとしても、間葉系幹細胞のトップランナーである馬渕先生と一緒に基礎研究を進められるのは、本当に心強いです。また、臨床の部分でも、同じ建物内に羽田クリニックがあり、整形外科や婦人科、眼科などの先生方と綿密な連携がとれるのは大きいですね。実際、この場所には医師の方もいらっしゃいますので、現在の臨床現場で感じている不安などをお聞きしながら課題を見つけ、新しいプロジェクトにつなげています。
——「再生・細胞医療開発講座」の設立から1年が経過しますが、同じ場所で共同研究を行うメリットや可能性をどう感じていますか?
野中 やはり、同じ場所で活動することによって円滑にコミュニケーションがとれる点ですね。それから、馬渕先生がお持ちのネットワークを通じて交流の輪が広がったことも大きいです。これまでロート製薬とは接点がなかった人たちと知り合い、一緒に再生医療を盛り上げていくための活動にもつながっています。おかげさまで想像以上に世界が広がったと感じていますね。
馬渕 私も、気軽にロートのみなさんに相談できるので、本当に助かっています。ロートの再生医療チームのメンバーは、人柄とチームワークが素晴らしくて、組織的に対応し実現に向けてトライアルをしてくれます。そのチームワークのパワーは、まるでブルドーザーのように強力です。
いずれ細胞は自由自在にデザインできる時代に?!
再生医療の発展と未来の形

——共創を活かし、再生医療、間葉系幹細胞の技術を使ってお二人が実現したいことを教えてください。
野中 いつか全ての細胞を人工的にデザインできるようになると思います。そうなれば、患者さん本人の細胞やドナーから提供された細胞を使わなくても、間葉系幹細胞の性質をもった「人工細胞」で治療ができる時代が訪れるかもしれません。
もちろん、口で言うほど簡単なことではありません。わたし達は病気を治そうと研究しているわけですから、例えば、人工細胞が体内で暴走するようなことはあってはいけません。
——そこも含めて間葉系幹細胞を完全にコントロールできるようになれば、医療そのものが一気に発展しそうです。
野中 そうですね。現時点でハッキリとしたゴール地点が見えているわけではありませんが、私たちの研究を突き詰めていった先にはそんな世界もあるのではないかと思います。
——馬渕先生はいかがでしょうか。
馬渕 まず、野中さんのお話にとても共感します。その上で、僕はこの再生医療を通じて、日本の人たちが自国への自信や期待を取り戻すきっかけになったらいいなと思っています。この再生医療の分野で山中先生がノーベル賞を受賞されたのは大きな希望ですし、再生医療を実用化・産業化して世界中の医療に役立てることができたら、日本に誇りを持つ人も増えるのではないでしょうか。
最後に夢みたいな話をすると、もしかしたら10年後、20年後には個人が自宅で自分の細胞を増やして、健康管理に役立てるみたいなことが当たり前になるかもしれません。現実味が無い話に聞こえるでしょうが、iPhoneやChatGPTのような技術が私たちの生活を大きく変えることなど、20年前にはまるで想像できなかったですよね。でも、背景にはそんな未来を信じ、ひたすら研究を続けていた人たちがいたわけです。
ですから、僕らもそんな世界が訪れることを信じて、研究を前に進めていきたい。そして、その礎を藤田医科大学とロート製薬と羽田で築いていき、未来の健康管理や医療のあり方を切り開いていければと思っています。

